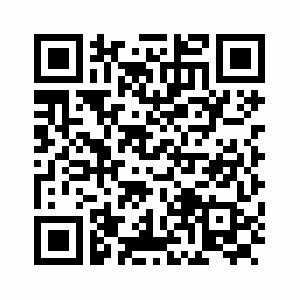1月 2022
1月 2022のブログ
みんなが気になる【海外大学費用】の徹底解説!マレーシア留学編
海外大学というと、アメリカやイギリス、カナダ、オーストラリアを思い浮かべる方が多いと思います。 しかし、現在、海外大学の進学を目指す人に注目されているのが、「マレーシア」なんです! この記事では、マレーシアの大学へ進学した場合の全費用をご紹介します。 * 全ての金額は、2021年12月付けのレート(1マレーシアリンギットMYR=27円、または1ドル=113円)で計算しています。 マレーシア大学の授業料 海外大学費用で一番大きな出費となるのが「授業料」です。 マレーシアは、イギリスの教育システムの影響を強く受けているため、基本的に総合大学は3年制です。 入学後は、すぐに専門分野の授業を受けることになります。 総合大学 マレーシアでは、国立・公立大学と私立大学の数はほぼ同じです。 平均の年間授業料 公立大学 約30万円 私立大学 約80万円 欧米へ大学進学する場合と比べると、授業料は1/3以下です。 具体的な年間の授業料 ここでは、留学生に人気の大学トップ5の授業料をご紹介します。 マラヤ大学(The University of Malaya) 公立大学 マレーシアで一番古い大学であるマラヤ大学は、世界で最も優れた100大学の一つです。 年間の授業料 約32万円〜 トゥンクアブドゥルラーマン大学カレッジ(Tunku Abdul Rahman University College) 私立大学 クアラルンプールにあるトゥンクアブドゥルラーマン大学カレッジは、アジアを中心に、多くの留学生を積極的に受け入れています。 年間の授業料 約44万円〜 マレーシア国民大学(National University of Malaysia) 国立大学 校舎、図書館の他に、郵便局、銀行、さらには、ゴルフ場、プール、スタジアム、病院までキャンパス内にあるマレーシア国民大学は、東南アジアでもっとも重要な大学の一つです。 年間の授業料 約12万円〜 マレーシア・プルリス大学(University of Malaysia Perlis) 公立大学 2001年に創立されたマレーシア・プルリス大学は、比較的新しい大学ですが、多くの外国人留学生が在籍し、国際色豊かな環境で勉強することができます。 年間の授業料 約17万円〜 マレーシア・プトラ大学(University Putra Malaysia) 国立大学 もともと、農科大学として創立されたマレーシア・プトラ大学は、農学、工学、医学を中心にマレーシアでもトップレベルの大学として知られています。 年間の授業料 約47万円〜 教材費 授業料の他に必要になるのが教材費です。 マレーシアは、相対的に教科書は高めです。 専攻によって必要な数は異なりますが、年間で約10万円近くかかる場合もあります。 また、学科によっては、画材やパソコンなど、別途に必要になります。 現地での生活費 生活にかかる費用を、きちんと把握しておくことが大切です。 物価が安いというイメージがあるマレーシアですが、実際はどうでしょうか? ここでは、人気大学があるクアラルンプールとカンガーに滞在するための、1カ月の生活費例をご紹介します。 クアラルンプール 水道光熱費 約5千円 インターネット 約3千円 シェアルームの家賃 1万円〜 学生寮 マラヤ大学の場合 9千500円〜 カンガー(プルリス州) 水道光熱費 約7千円 インターネット 約1千300円 シェアルームの家賃 9万円〜 学生寮 マレーシア・プルリス大学の場合4カ月契約 4万円〜 https://bokuryuu.com/how-to-find-destination/ 食費 物価が安いと言われるマレーシア。 外食をメインにしても1カ月2万円前後ほどです。 地元の食材を使って、自炊を中心とした生活をする場合は、1カ月1万円以内で収まります。 その他の費用 その他に留学準備の段階で必要となる費用は以下の通りです。 学生ビザ マレーシアの大学に進学する場合は、学生ビザの申請が必要です。 学生ビザの申請手続きは、学校がマレーシア教育省にビザの申請を行います。 ビザの申請は基本的に無料ですが、申請代行費用が発生する場合があります。 マレーシア・プトラ大学の場合:大学の授業料を支払う時に、学生ビザ申請代行費用の一部に当たる約3万円を支払い、現地到着後に残りの代行費用、約3万円〜5万円を支払います。 その他に、マレーシアの学生ビザには以下のような特徴があります。 学生ビザ申請時の年齢は18歳〜35歳 週20時間までの労働が可能 留学保険 医療・生命・損害分野と全てが手厚く補償され、日本語で対応してもらえる「日本の留学保険」に加入することをお勧めします。 サポート内容で異なりますが、1年のプランで14万円〜27万円です。 現地までの渡航費 シーズンによって航空券の料金が大幅に変わります。 直行便の多いマレーシアは、往復7万円〜が相場です。 パスポート申請 海外に行く場合、必ずパスポートが必要になります。 費用は、10年で1万6千円、5年で1万千円です。 まとめ この記事では、具体的な金額を提示しながら、 マレーシアの大学の授業料 教材費 現地での生活費 その他の費用 についてご紹介しました。 学費が高いことを理由に、海外大学の進学を断念されていた方にとって、マレーシアは魅力的なのではないでしょうか? さらに、海外大学費用を抑えるコツもたくさんあります。 https://bokuryuu.com/the-costproblems-for-studying-abroad/ https://bokuryuu.com/how-to-keep-costs-down-for-studying-abroad/ また、マレーシアには次のような特別プログラムもあります。 マレーシアの大学を卒業すると同時に、海外の提携大学の学位も取得できる「デュアルディグリープログラム」 マレーシアの大学で学びながら、アメリカ、イギリス、オーストラリアなどの大学にも通うことができる「ツイニングプログラム」 https://bokuryuu.com/malaysian-education-system/ もっと詳しく知りたい方は、一度留学エージェントに相談してみましょう。 このほかにも、現地オフィスや現地の留学生から直接最新の情報を入手できるほか、費用を抑えて留学するアドバイスやお手伝いもしてくれます。 https://bokuryuu.com/about-agent-of-studying-abroad/ 参考サイト学費比較 留学生に人気のマレーシアの大学 https://worldscholarshipforum.com/best-universities-malaysia/ 学費比較サイト https://collegelearners.com シェアルーム情報 https://www.ibilik.my/rooms/kuala_lumpur 物価比較サイト https://www.numbeo.com…
2022/01/04海外大学へ編入したい人必見!【日本から編入】するには?
「海外大学へ進学」というと、どのようなイメージがありますか? 卒業を迎える高校生のための進学先、スキル・キャリアアップを目指す社会人留学、と思い浮かぶかもしれません。 現役大学生の「留学方法」といえば、交換・認定留学、長期休暇の語学留学、休学してワーキングホリデー、と思っている人が多いのではないでしょうか?! 実は、日本の大学に在籍している学生も、卒業を待たずに「海外大学へ進学」できる方法があります。 それが「編入」です。 この記事では、海外大学編入の方法、編入する前にするべき準備、そして国ごとのおすすめ大学をご紹介します。 ぜひ参考にしてくださいね! 海外大学へ編入する前にすべきこと 日本の大学から海外大学へ編入する方法を詳しく知る前に、次の3点を明確にしておきましょう。 ①海外大学へ編入する理由を明確にする 海外の大学へ編入する理由を、できるだけ明確にしましょう。 なぜ日本の大学ではダメなのか? なぜ環境を大きく変えてまで海外の大学へ編入したいのか? など、編入する理由を明確にすることで、大学を選ぶ時だけでなく、長期海外留学をする上でも自分を見失わず軸がブレなくなります。 ②どんな分野を学びたいのか明確にする 海外の大学で学びたい専攻分野を明確にしましょう。 今まで学んでいる分野の延長なのか? それとも全く別の分野なのか? 場合によっては、大学選びや編入方法も大きく変わります。 ただし、現在専攻している分野と、全く別のものを選択する場合には、編入自体が難しい場合もあるので注意が必要です。 ③海外大学へ編入してどうなりたいかを明確にする 帰国後は日本国内の外資の企業への転職を目指す! 卒業後は海外で就職したい! など、海外大学へ編入することで、自分がどうなりたいのか、将来のビジョンを明確にしましょう。 なぜ海外の大学へ編入したいのか? どんな分野を学びたいのか? と重複しますが、将来の自分のビジョンを思い描くことで、海外大学への編入はより良いものになります。 海外大学へ編入するための方法 日本の大学から海外大学へ編入する方法は、大きく分けて2つあります。 日本の大学へ入学後、海外大学へ編入する方法 海外のコミュニティカレッジに入ってから大学編入を目指す方法 それぞれについて説明します。 ①日本の大学へ入学後、海外大学へ編入する方法 日本の大学から海外大学へ直接編入する場合、入試・編入試験はありません。 編入先の募集要項を参考に、必要書類をまとめ出願します。 その際に重要になるのが、日本の大学での成績です。 編入先の大学によってさまざまですが、英語の語学力もある一定の基準以上を求められることがあります。 単位の移行に関しては、日本の大学と編入先の海外大学により異なります。 日本の大学で取得した単位を、海外大学へ移行できない場合もあるので、事前に調べておくことが大切です。 移行できない場合、編入後に海外大学の卒業に必要な必須単位を取得しなければならないため、在籍期間が延長され、滞在費用も大きく変わってしまいます。 ②海外のコミュニティカレッジに入ってから大学編入を目指す方法 海外には、日本の短大のような「コミュニティカレッジ」と呼ばれる公立大学があります。 教育課程は2年間で、学業コースもしくは就職訓練コースを選択できます。 コミュニティカレッジは4年制の大学と比べて、入学時に求められる英語力と授業料が比較的低いのが特徴です。 英語が苦手な人は、まずはコミュニティカレッジでしっかり英語を学んだ後、大学編入を目指すことも可能です。 コミュニティカレッジと提携している大学も多く、名門大学への編入も夢ではありません。 ただし、編入するためには2年間、良い成績をキープするためにしっかり勉強しましょう。 https://bokuryuu.com/community-college/ 海外大学へ編入するために必要な準備 海外大学への編入条件は各大学によって異なりますが、一般的には高い語学力を求められます。 また、授業料や現地での生活費を含む留学費用がかかります。 ①語学力 海外大学へ編入する場合、ある程度の語学力は必須です。 生活していくうえではもちろんのこと、大学の講義では積極的に意見を求められる「参加型」授業が主流のため、自分の意見を英語で相手に伝えることが必要になります。 レポート・エッセイの提出も頻繁にあることから、学術的レベルの英語力があったほうが良いでしょう。 英語能力試験で求められるレベルは、編入先の大学や学部によって異なるので、入学を希望する大学の募集要項で、求められる語学力を確認してください。 大学で学ぶ場合、語学力は大きな壁になるので、日本にいる間にしっかり準備をしましょう。 ②費用 海外大学への編入には、多大な費用がかかります。 また、学費以外にも現地での生活費用も必要です。 滞在する地域によって家賃や食費は大きく異なりますが、現地でのアルバイト制限も考慮すると、事前にまとまった費用を準備する必要があります。 奨学金制度などの支援制度もあるので、申請条件や制度の内容を理解しておくことが大切です。 https://bokuryuu.com/compare-costs/ ③計画 編入したい大学が決定したら、まずは編入できる時期や募集要項を時間をかけて調べましょう そして、その編入時期や難易度から逆算して計画を立てていきましょう。 そうすることで語学の学習や費用を、いつまでに、どのような手続きや準備をすれば良いのか明確になります。 日本の大学から編入しやすい海外大学リスト 日本の大学から編入ができる海外大学は、数多くあります。 しかし、 どんな目的で行くのか どんな分野を学ぶのか 将来にどうつなげたいのか 大学院へ進学したいか などで、編入先は変わってきます。 まずは、編入先を選ぶ前に、理由や目的を明確にしましょう。 ここでは、人気の留学先アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアの4カ国の中から、編入がしやすいおすすめの大学を紹介します。 詳細はページに関してはリンクが貼ってあるので、ぜひご覧ください! ①アメリカ 留学先として一番人気の国「アメリカ」。 外国からの留学生だけでなく、世界中からの移民が生活しているため、必然的に他の国の文化・風習・歴史について学ぶ機会がたくさんあり、どこにいてもグローバルな環境に身を置くことになります。 世界中にネットワークを作ることができるのもアメリカ留学の魅力です。 フロリダ大学 ノースダコタ大学 バージニア大学 https://bokuryuu.com/how-to-study-at-a-university-in-america/ ②イギリス 教育や研究のクオリティーが、世界トップレベルとして有名なイギリス。 最先端の設備が整っているキャンパスも多く、「イギリスの大学を卒業=世界に通用するスキルが身についている」と世界中の企業に評価されています。 アメリカやカナダに比べると日本人留学生の数が少ないため、勉強に集中できる環境が約束されています。 ヨーク大学 マンチェスター・メトロポリタン大学 ブライトン大学 https://bokuryuu.com/how-to-study-at-a-university-in-uk/ ③カナダ 教育水準の高い国として知られているため、大学進学先としてアメリカの次に人気がある国「カナダ」。 卒業後は就労ビザがもらえ、永住権が取りやすいことから、世界中から留学生が集まってきます。 トロント大学 マギル大学 アルバータ大学 https://bokuryuu.com/how-to-study-at-a-university-in-canada/ ④オーストラリア 海に囲まれ、自然溢れる国「オーストラリア」は、多様な人種や文化が行き交い、フレンドリーな国民性を誇るこの地は、世界中から学生が集まります。 また、「住みやすい国」としてアジア人も多く、語学留学やワーキングホリデー制度を利用した日本人留学生にも人気です。 クイーンズランド大学 メルボルン大学 マッコーリー大学 https://bokuryuu.com/how-to-study-at-a-university-in-australia/ まとめ【海外大学へ編入するための準備しよう!】 日本の大学から海外大学へ編入するためには、語学力、費用、計画、編入先などの下調べは、全て大切な準備です。 しかし、より重要になってくるのは、 なぜ日本の大学ではなくて海外大学へ編入したいのか その編入先で何を学びたいのか 編入後どうなりたいのか 卒業後の進路はどうするべきか ということです。 目的を明確にでいると、必然的にTOEFLなどの英語能力試験の対策や留学費の費用などの計画を、自分の状況に応じて準備を始めることができます。 いろいろなサイトでメリット・デメリットをしっかり調べた上で、自分に合う編入先を決めましょう。 最後に編入しやすい海外大学のある国を、一覧にしてまとめておきます。 アメリカ イギリス カナダ オーストラリア 国土も大きい英語圏の国々は、国際色豊かな留学生が多いため、大学内の外国人向け制度も柔軟に受け入れる体制が整っています。 また大学独自で、留学生向けのインターンシップ情報、人材育成プログラム、キャリア・就職・採用情報関連のイベントも開催されています。 ご自身の希望がかなう留学先を決めてくださいね! 「やることが多くて準備をどこからスタートすればよいかわからない」という方は、「ぼくらの留学」にご相談ください! みなさんの悩みや不安の解消をお手伝いをするカウンセラーは、すべて留学経験者。 各種手続きのお手伝いだけでなく、現地オフィスや現地の留学生から、ネットでは検索できない最新の情報を入手できるほか、費用を抑えて留学するアドバイスもしています。 留学エージェントについての記事もあわせてご覧ください! https://bokuryuu.com/about-agent-of-studying-abroad/…
2022/01/04高いスキルを身に付けたい大学生・社会人が選択する【海外大学院の進学】について解説します!
「他の人と差をつけたい!」と考える大学生や社会人に人気なのが海外大学院への留学です。 ここでは、学問を極め、実践的で高いスキルを身につけることができる【海外大学院の進学】について、わかりやすく解説します! 海外の大学院の基礎知識 日本では特別なように感じる「大学院への進学」。 しかし、海外では大学へ進学した多くの学生が、より知識を身につけるために大学院へ進みます。 まずは海外の大学院の基礎知識をみていきましょう。 なぜ大学院に入るのか 日本では、「大学院=学者や教授になる」と考えている人が多いですが、海外では 学士号=専門分野の教養がある 修士号=専門分野のスペシャリスト と考えられています。 また、大学院を卒業して社会に出ると、 大学卒業者よりも収入が高い 出世が早い などのアドバンテージがあります。 そのため、社会人がキャリアアップを目指すために、大学院へ入るケースが大変多いのが特徴です。 アメリカを例で見ると、大学院生の平均年齢がなんと33歳! 学生全体の22%が40歳以上、14%が40歳〜50歳、そして8%が50歳以上です。 大学院で学ぶことにより、学生は学んだことの知識をさらに深めスペシャリストとして活躍でき、社会人は今まで身につけてきたスキルを学位として証明し、キャリアアップを目指すことができるのです。 大学院の種類 大学院の種類は大きく分けて「2つ」あります。 グラジュエイトスクール(Graduate school/Graduate School of Arts & Sciences) 社会学、経済学、文学、哲学などのアカデミックな分野の研究を行います。 日本の「大学院=学者や教授になる」に近いイメージです。 プロフェッショナルスクール(Professional school) 日本でも知られているMBA(Master of Business Administration:経営大学院)をはじめ、ロースクール(Law school:法科大学院)、医学、教育学など、スペシャリストの養成を行っています。 大学院に入るほとんどの社会人が、このプロフェッショナルスクールで学んでいます。 大学院で取得できる学位 大学院で取得できる学位はマスターディグリー(Master's degree)と呼ばれ、日本の「修士号」にあたります。 国によって異なりますが、ここでは大学院で取れる代表的な学位をみていきましょう。 Master of Arts (MA):文学修士号 Master of Science (MS、イギリスではMSc):理学修士号 修了期間 アメリカ、カナダの場合は2年間で、基本的に9月が入学時期、6月が卒業時期になります。 長期休暇(春、夏、冬休み)があるため、実際に講義があるのは2年間でトータル19カ月ほどです。 イギリスは1年間で、入学と卒業のタイミングが9月です。 長期休暇がないため、12カ月間をフルに使った修了期間を設けています。 大学院の年間授業料 大学院によって費用は異なりますが、ここでは国別に平均の年間授業料をご紹介します。 年間授業料の例 アメリカ:約550万円 カナダ:約400万円 オーストラリア:約300万円 イギリス:約500万円 マレーシア:約100万円 出願書類 アメリカの大学院を例に、出願時に提出する必要書類をチェックしてみましょう! 推薦状*(最低3通) 英文のエッセイ 大学の成績証明書 (Grade Point Average/GPA**換算のもの) TOEFLのスコア 大学院用共通テスト(Graduate Record Examination/GRE***)のスコア そのほかにも専門分野によっては、必要書類が追加される場合があります。 *推薦状:審査にもっとも重要な書類になるので、学生であればゼミの担当教師や学部長など、社会人であれば大学時代の恩師や会社の上司など、人選が非常に大切です。 **Grade Point Average/GPA:アメリカの大学や高校で使用されている成績評価指標で、日本でも採用している大学が増えています。 ***Graduate Record Examination/GRE:アメリカやカナダの大学院に進学する際に受ける共通試験で、論文(Analytical Writing)、英語(Verbal Reasoning)、数学(Quantitative Reasoning)の3つの項目があります。 海外大学院進学のメリット・デメリット 海外の大学院に興味を持っている人に、ぜひ知っていただきたいメリットとデメリット。 メリットはもちろんのこと、事前に知っておくことで、デメリット対策ができます。 メリット 世界中にネットワークができる 外国人留学生を多く受け入れている海外の大学院。 同じ専門分野を学ぶために集まった学生たちと、毎日授業を受けることで、学生同士の絆が強まります。 また、世界中からやってくる一流の教授に出会うことができるので、インターンシップや正規雇用から他の大学の研究所などの情報が得やすいのも大学院進学のメリットです。 就職に有利 30歳以下の大学院進学率は、日本では約7.5%なのに対し、海外では次のとおりです。 オーストラリア約30% イギリス 約25.7% アメリカ 約9% このように、海外で大学院への進学率が高いのは、マスターディグリーを取ると就職時の待遇(給料・ポジション)が大変良いためです。 就労ビザの取得が難しいとされるアメリカでも、マスターディグリーを取得していれば簡単に審査が通ります。 その理由は、マスターディグリーは「スペシャリスト」として社会的に認知されているためです。 修士号のアドバンテージを踏まえると、社会人になってから大学院へ入り直す人が多いのもうなずけます。 論理的思考力が身につく 海外大学院では、論述テストやレポート提出で成績の評価がつけられます。 そのため、課題をこなしていけばいくほど、論理的に物事を考えてまとめる力がついていきます。 相手を納得させるため、自分の考えを論理的に主張するテクニックをしっかり身につけることは、英語力の証明にもなります。 デメリット 卒業が大変 海外の学校は、入るのは簡単で出るのは難しいという現実です。 海外大学の進学でも言われることですが、特に大学院の場合、1年〜2年と修了期間が短い上に、 自分の専門分野の研究 論述テスト 課題レポート 講義(+予習・復習) 専門分野によってはグループで行うプロジェクトもあるため、その打ち合わせなどもこなさなければなず、とてもハードな日程をこなせなければなりません。 もちろん、専門分野によって異なりますが、在学中は勉強に専念できるような環境作りを心がけなければなりません。 このような努力をして取得する「マスターディグリー」だからこそ価値があり、世界で「スペシャリスト」として認められるのです。 日本の就活の波に乗り遅れる 日本と海外の大学の入学・卒業のタイミングが違うため、日本で就職を目指す場合「新卒枠」から外れてしまいます。 そのため「大学卒業者」もしくは「留学生枠」で就活をしなければなりません。 まとめ この記事では、海外の大学院に進学したいと考える大学生・社会人のために、 海外の大学院の基礎知識 海外大学院進学のメリット・デメリット をご紹介しました。 海外の大学院へ進学することは、ある程度の覚悟が必要ですが、「バチェラーディグリー」を取得している学生が当たり前になりつつある今だからこそ、価値があると言えるでしょう。 また、普通の留学では出会うことができないような、専門分野に置ける世界の一流の人材とコネクションを作ることができるのも、社会人になってから大学院に入る人が多い理由と言えます。 ぜひこの記事を参考になさってください! 特に初めての方や、留学で失敗したくないという方は、一度留学エージェントに相談してみましょう。 現地オフィスや現地の留学生から直接最新の情報を入手できるほか、費用を抑えて留学するアドバイスやお手伝いもしてくれます。 https://bokuryuu.com/about-agent-of-studying-abroad/ 参考サイト アメリカの大学院生の年齢に関する記事:graduateguide.com 国別の大学院の学費情報:mastersportal.com 大学院進学率:stats.oecd.org…
2022/01/04卒業・学位取得のために知っておきたい!【海外大学の単位】システムと落とさない方法
学習方法、講義のスタイル、成績の評価方法が日本とは異なる海外大学。 正規留学生として進学する場合、各国のシステムに沿って「単位」を取っていかなければなりません。 この記事では、みなさんの留学が成功することを願い、海外大学の単位システムと単位を落とさないための学習方法をご紹介します! 海外大学の単位 「単位」は英語で「アカデミッククレジット(academic credit)」もしくは単に「クレジット(credit)」といいます。 単位は、大学で学位を取得するために必ず取らなければならず、学生の勉強への意欲や努力、その結果を評価するためのシステムです。 海外大学を卒業するには、かなりの勉強量が必要になります。 できるだけ、無駄な努力を避けるためにも、実際に大学に進学する前に、単位のシステムを理解しておいたほうがよいでしょう。 単位システム 海外大学では、次のシステムが一般的です。 ECTS(European Credit Transfer and Accumulation System):日本語では「ヨーロッパ単位認定システム」と言われている、ヨーロッパ各国の大学で共通に用いられる単位システム SCH(semester credit hour):日本語では「学期単位」言われる、アメリカの単位システム 評価形式 学位を得るために必要な単位は、実際にどのよう評価されるのでしょうか? 基本的に次の項目の評価を基準に、単位を取れるかが決まります。 授業の出席率:ただ出席するだけではなく、授業中の発言頻度や積極性が見られる 授業中に行われる小テストの結果 課題レポート内容 プロジェクト・研究の作業:積極的な参加が求められる 口頭・筆記による中間・期末試験の結果 国別のシステム ここでは、アメリカ、オーストラリア、イギリスの3カ国の一般的な単位システムをご紹介します。 もちろん、大学や専攻コースによって異なるので、希望校の単位システムはしっかりチェックしましょう! アメリカ アメリカの大学では、「1時間の講義+2時間の準備=1単位」に基づく単位システム「SCH」を採用しています。 学年を上がるために必要な一般的な単位数は次の通りです。 1年生(Freshman) 29単位 2年生(Sophomore) 30単位 3年生(Junior) 29単位 4年生(Senior) 30単位以上 例えば、セメスター制(二学期制)の大学の場合、 15時間の講義+30時間の予習を含む講義の準備=450時間の学習 で、各学期に15単位を取得できる計算になるので、この学習時間をキープできれば、4年間で卒業することができます。 オーストラリア オーストラリアの大学では、共通の単位システムはありません。 そのため、大学・専攻コースによって、独自の単位システムが採用されているのです。 他の大学へ編入する場合は、オーストラリア資格フレームワーク(Australian Qualifications Framework、AQF)というオーストラリアの教育水準認定機関によって、単位交換の審査が行われます。 イギリス イギリスはヨーロッパの単位認定システム(ECTS)に加盟しています。 そのため、同じヨーロッパの加盟国内の大学に簡単に編入できます。 ECTSの単位を取得するための学習時間は次の通りです。 1単位=25〜30時間(講義+準備)3年間で学士を取得するには、年間で60単位を取る必要があります。 海外大学で単位を落とさない方法 海外大学で単位を落とさないためには、「勉強方法」を知ることです。 学位取得の目標を実現するために、次のポイントをしっかり抑えましょう。 日本にいる間にするべきこと 自分の意見を言えるようにする 自分の意見を持ち、他者に論理的に伝えることは、海外で生活する上で必要不可欠です。 渡航する前に、日常生活の中で「自分の意見をもつ」習慣を身につけておきましょう。 海外大学の授業は、日本とは違い、ディスカッションを中心に行われていきます。 授業内で発言をしなければ、出席をしていても成績評価の対象にならないのです。 そのため、専門コースだけでなく、歴史、政治、経済などをテーマに自分の意見を言えるように準備しておきましょう。 英語力をつける 海外の大学では、「授業を受ける」「話し合う」「課外レポートを書く」は、全て英語でおこないます。 大学に入ると、単位を取る勉強で忙しくなり、英語の勉強をする時間はありません。 そのため、日本にいる間に、できるだけ英語力をつける準備をしましょう。 出願条件に必要な英語能力試験のスコアをとるだけでなく、英会話や国際交流会などを利用して外国人とコミュニケーションを取ることに慣れておきましょう。 海外の大学でするべきこと 予習・復習をする 海外の大学の授業は「予習」と「復習」が必要です。 一般的に新学期の最初の週は、各科目を担当している教員から次のようなオリエンテーションがあります。 学期中に行う授業内容 課題レポート対策 試験方法 この他にも、期間中に読むべき本なども指定されます。 このオリエンテーションにより、予習対策ができるのです。 また、授業後は必ず復習もしましょう。 自分が書いたノートを読み返したり、録音OKな授業であれば、帰宅後に講義を聞き直すと理解度が上がります。 積極的に質問する 授業や課題でわからないところがあれば、必ず教員に質問しましょう。 授業中に質問するのが理想的ですが、授業が終わった直後でも大丈夫です。 「分からない」ことよりも「分かったふり」をするほうが、学習をする上で大変なことになって行くので、できるだけその場で問題を解決するようにしましょう。 質問する姿勢は「学習へ対するやる気」という評価にもなります。 授業に参加する 海外大学の授業は、「参加する=出席」です。 そのため、授業中に一度も発言しなければ、教室にいたとしても評価されないこともあります。 授業中に発言するコツがいくつかあります。 授業の予習をしっかりしておく:ディスカッションのテーマは事前に知らされている場合があるので、できるだけ予習して置くと自分の意見が言いやすくなる 手を挙げる:ディスカッションで発言したいときに「手をあげる」ことで、自分の意見を話すタイミングを作ることがでる 自分から質問を投げかけてみる:話し合いからずれてしまっても構わないので、自分からテーマに沿った質問を投げかけてみましょう。 課題レポートのチェック 基本的なレポートの書き方のルールを抑えることはできても、母国語でない日本人が完璧な課題レポートを仕上げるのはとても難しいことです。 そのため、仕上げた課題レポートは、一度英語が母国語の人にチェックをしてもらいましょう。 大変な時は相談する 本当に勉強が大変な時は、必ず誰かに相談しましょう。 チューター、学生サポートセンターなど、大学には留学生を助けるシステムがあります。 また、教員とできるだけコミュニケーションを取ることで、単位を落とさないようなアドバイスをもらえることもあります。 大変な時は一人で抱え込まず、必ず大学の誰かに相談しましょう。 まとめ ここでは、卒業・学位取得のための知識として 海外大学の単位 国別のシステム 海外大学で単位を落とさない方法 についてご紹介しました。 「海外の大学は、入学はできても卒業するのが難しい」という言葉をよく耳にします。 英語が母国語ではない日本人が、単独で海外に行き、慣れない生活習慣と慣れない学習環境で大学に行くのですから、大変なのは当たり前です! だからこそ、日本にいる間にしっかり情報を集め、準備することで「難しい」に備えることができるのです。 留学は情報収集からはじめ、出願手続きやビザの申請など、やらなければならないことがたくさんあります。 特に初めての方や、留学で失敗したくないという方は、一度留学エージェントに相談してみましょう。 現地オフィスや現地の留学生から直接最新の情報を入手できるほか、費用を抑えて留学するアドバイスやお手伝いもしてくれます。 https://bokuryuu.com/about-agent-of-studying-abroad/ 参考サイト 海外大学の単位システム:www.bachelorsportal.com…
2022/01/03【海外留学】イギリスの大学に編入する5つの方法!ケース毎にわかりやすく解説
「日本の大学からイギリスの大学に編入したい」「イギリスの大学に編入する方法を知りたい」と思っている方もいるのではないでしょうか。 教育制度は国によって異なるので、わからないことも多いはずです。 結論から言うと、日本の大学で取得した単位を移行する方法やイギリスの教育プログラムを利用して編入する方法があります。 今回は、イギリスの大学における教育・編入制度や5つの編入方法をご紹介します。日本の大学からイギリスの大学へ編入を検討している方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。 この記事を読むと、イギリスの大学が導入している編入制度がわかり、海外進学の選択肢が広がります。 イギリスの大学における教育・編入制度について知ろう イギリスの大学と日本の大学とは教育システムが大きく異なります。 ここでは、イギリスの大学における教育・編入制度について解説します。 日本の高校卒業資格だけでは入学できない イギリスの大学には日本の高校卒業資格だけでは入学できません。イギリスでは大学入学の時点で、日本の大学1年次で学ぶレベルの一般教養が求められるからです。 留学生がイギリスの大学に進学する場合は、下記の条件を満たしている必要があります。 自国の大学などの高等教育を1年間修了している イギリスの教育機関が開講している「ファンデーションコース」と呼ばれる大学準備コースを1年間修了している イギリスの大学は基本3年制 イギリスの大学は3年制が一般的です。日本やアメリカの大学のように1年次は一般教養を学ぶのではなく、入学後すぐに専門科目と選択科目の講義がスタートします。 入学する難易度は高いものの、短い期間で学位を取得できる点はメリットだといます。 しかし、イギリスの中でもスコットランドは教育システムが異なり、4年制を採用している大学が多いです。 イギリスの大学は2学期制が一般的 多くのイギリスの大学は2学期制を採用しています。1学期に60単位、1年間に120単位、卒業までには合計360単位を取得するのが一般的です。単位を落としてしまった科目がある場合は、再履修しなければなりません。 新1年生以外は各学期に入学したり、ほかの大学に単位を移行して編入したりできます。また、休学して残りの単位を復学後に取得する、学期の途中で専攻分野を変更するという選択肢もあります。 通っている大学でサマースクールやウィンタースクールなどが開講されるのであれば、その間の単位を取得して通常よりも早く卒業が可能です。 イギリスの大学に編入する5つの方法 イギリスの大学に編入する方法は下記の5つがあります。 日本の大学からイギリスの大学へ編入 インターナショナル・ディプロマを受講してから大学2年次に編入 パスウェイプログラムを利用して大学2年次に編入 Top-upプログラムを利用してイギリスの大学へ編入 公立カレッジから提携大学に編入 1つずつ詳しく解説しますね。 日本の大学からイギリスの大学へ編入 日本の大学で取得した単位を移行して、イギリスの大学に編入する方法が最も一般的です。 イギリスの大学に編入するには、下記の単位移行の条件を満たしている必要があります。 日本の大学の専門分野と、イギリスの大学で学びたい専門分野が同じ 日本の大学で履修した教科と、イギリスの大学の履修内容が同じ 要するに、単位数ではなく「専門分野と履修した教科内容が一致していること」を条件に単位が認められます。実際にどの単位が認定されるのかは編入先の大学によって異なります。 インターナショナル・ディプロマを受講してから大学2年次に編入 日本の大学で1年次を修了していれば、イギリスの大学に直接入学する道もあります。しかし、英語力や一般教養などに不安がある方は「インターナショナル・ディプロマ」という大学準備コースを受講してから、大学2年次に編入する方法がおすすめです。 インターナショナル・ディプロマに1年間ほど通えば、大学進学に必要なレベルの英語力と一般教養を身に付けることができます。 インターナショナル・ディプロマを受講するには、下記の条件を満たしている必要があります。 IELTS5.0以上 ファンデーションコースか大学の1年次を修了している パスウェイプログラムを利用して大学2年次に編入 日本の大学や教育機関が提携している「パスウェイプログラム」を利用して、イギリスの大学2年次に編入する方法です。 パスウェイプログラムを利用するには、下記の条件を満たしている必要があります。 日本の大学または短大の1年次を修了している 編入先の大学によって定められている成績(GPA)をクリア 編入先の大学によって定められている英語レベルをクリア 入学条件や受講できる専攻分野は各大学によって異なるので、事前に確認が必要です。 Top-upプログラムを利用してイギリスの大学へ編入 「Top-upプログラム」という編入制度を利用すれば、途中でイギリスの大学へ編入できます。ただし、「HND(Higher National Diploma)」という高等教育レベルの認定を受ける必要があります。 通常は2年間大学に通い卒業した後でHNDを取得しますが、いくつかの大学では短期間で取得できるプログラムがあります。 公立カレッジから提携大学に編入 公立カレッジから提携している大学に編入する方法です。イギリスの公立カレッジは、もともと就業率を上げるための「職業訓練コース」がメインでした。 しかし、「ハイヤー・エデュケーション・カレッジ(Higher Education College)では提携大学に編入できるコースや大学と同じ学位が取れるコースが充実しています。 自分の目的に合ったカレッジを選べば、学位取得までの道を短縮できるでしょう。 まとめ【編入を利用してイギリスの大学に進学しよう】 今回は、イギリスの大学における教育・編入制度や5つの編入方法をご紹介しました。 最後にもう一度、イギリスの大学に編入する方法をまとめておきます。 日本の大学からイギリスの大学へ編入 インターナショナル・ディプロマを受講してから大学2年次に編入 パスウェイプログラムを利用して大学2年次に編入 Top-upプログラムを利用してイギリスの大学へ編入 公立カレッジから提携大学に編入 イギリスの大学に編入する方法はいくつかあるので、それぞれの特徴や利用条件を把握することが大切です。 編入制度を賢く利用すれば、世界大学ランキングの上位校への入学も夢ではありません。 …
2022/01/03海外大学留学に役立つ!【世界偏差値ランキング】受験システムを解説
日本で受験をする際に、必ず話題になるのが「偏差値」。「希望海外大学の偏差値がわからない」「私は偏差値が低いから、海外大学に進学することができないかも」と不安になっている人も多いのではないでしょうか? そんな方のために、この記事では海外有名大学の偏差値と海外大学の受験システムについて解説します! そもそも海外大学に偏差値はあるか 偏差値とはそもそも、一体なんでしょうか? 偏差値とは、試験の受験者全体の平均点数の中で、自分の成績の位置を表した数値の事です。 つまり「その試験を受けた人の中で、あなたの成績がどれくらいの位置にあるか」を表した指標で、平均点より低い点数を取ると「偏差値が低い」と位置付けられ、平均点より高い点数を取ると「偏差値が高い」と言うことになります。 海外大学の偏差値 結論から言うと、海外の大学には偏差値はありません。 なぜなら、海外大学に進学するためには入試ではなく、書類審査になるため、試験の点数から割り出す偏差値をつけることができないのです。 それでも、合格率などであえて割り出した「海外大学偏差値」の一覧は、次のようになります。 世界大学ランキング「トップ5」 オックスフォード大学(イギリス) 偏差値70相当 ハーバード大学(アメリカ) 偏差値80以上 スタンフォード大学 (アメリカ) 偏差値80以上 ケンブリッジ大学(イギリス) 偏差値73相当 マサチューセッツ工科大学(アメリカ) 偏差値80以上 6年連続「世界大学ランキング1位」のイギリスの名門オックスフォード大学が偏差値70相当と、「トップ5」の中で一番低いのがわかります。 ちなみに、世界大学ランキング35位の東京大学の平均偏差値が67〜72、61位の京都大学は60〜72なので、世界大学ランキングの評価と日本の偏差値が噛み合わないことがわかります。 海外大学の受験システムを理解しよう ここからは、偏差値・入試がない海外大学をどのように選び、出願するのか解説します。 海外大学の選び方 海外大学の選び方には次のようなステップがあります。 ステップ1:専攻コースを選ぶ まずは自分が何を勉強したいのか明確にし、それに準ずる専攻コースがある大学をいくつか選択する。 ステップ2:財政の確保 選んだ大学の中から、何らかの形で学費を払えるところを選ぶ。 多くの大学生は奨学金、学生ローン、長期休暇の労働などで学費をまかなっています。 ステップ3:出願条件と自分の成績を照らし合わせる 専攻コースを決め、学費をなんとか払える大学を選んだら、あとは自分の英語力や高校・大学の成績で入れそうなところに絞ります。 英語能力試験のスコアが足りない場合でも、英語の補習授業をとることなどを条件に入学できる大学もあるので、諦めずに調べましょう。 海外大学の出願方法 ここではアメリカの4年制大学を例に、海外大学の出願方法をご紹介します。 出願に必要な書類 海外の大学に出願するには、指定された必要書類をそろえ、大学共通のオンライン出願フォームから申請します。 大学や専攻コースにより異なりますが、一般的な出願時に必要な書類は次の通りです。 TOEFLやIELTSなどの英語能力試験のスコア 大学によって求められる「英語能力試験のスコア」は異なります。 ここでは先ほど紹介した、世界大学ランキング「トップ5」のTOEFL iBTスコアをみてみましょう。 世界大学ランキング「トップ5」のTOEFL iBTスコア オックスフォード大学(イギリス) 110点〜 ハーバード大学(アメリカ) 100点〜 スタンフォード大学 (アメリカ) 100点〜 ケンブリッジ大学(イギリス) 110点〜 マサチューセッツ工科大学(アメリカ) 90点〜 SAT(Scholastic Assessment Test) SATは、もともとアメリカの義務教育を受けた生徒を対象とする試験で、大学進学を目指す外国人も対象になっており、読解・英語・数学の3科目を通して、大学の授業についていくのに必要な基礎学力を測るテストです。 その他の書類 モチベーションレター、高校または大学の成績証明書、銀行の残高証明書、その他にも、推薦状、芸術分野であればポートフォリオも別途求められます。 手続きの流れ アメリカの大学に出願する際には、早期出願とレギュラー出願があり各大学により日程が異なるので、必ず事前に確認しましょう。 早期出願であれば11月までに必要書類を提出し、年末に合否通知を受け取ります。 レギュラー出願は、1月までに必要書類を提出し、3月〜4月に合否通知を受け取ります。 合否審査の基準は成績だけではない TOEFLやIELTSなどの英語能力試験のスコアやSAT試験をみて、「難しそう・・・」と諦めるのはまだ早い! 海外大学では、成績の他にも重要な合否審査の基準があるんです! モチベーションレター 出願時に必要な書類に入っている「モチベーションレター」。 実は合否審査に、もっとも重要な書類です。 成績が少し悪くても、このモチベーションレターをきちんと書くことで、合格に大きくつながります。 そのため、希望する大学に「いかに入学したいか!」という理由をしっかり書いて、自分らしくアピールすることが必要です。 課外活動 国によって異なりますが、一般的に、海外大学のオンライン出願フォームには「課外活動」について記載する欄があります。 主に中学3年生〜高校3年生の間に、授業以外で積極的に行った活動を記入します。 中学・高校はバスケットボール部で活動した(キャプテンだった!レギュラーだった!などのポイントもどんどんアピールしましょう) ボランティア活動に参加していた 夏休みに海外留学をした 幼い頃からピアノを習っている(コンクールや発表会に参加した場合も、記入しましょう) 海外では積極的に社会貢献する人が高く評価されるため、入学審査員に印象づけることができます。 成績が良くなくても海外の大学に行ける方法 「学校の成績が良くないから海外の大学に行けない・・・」「英語能力試験のスコアが全然足りない!」という方のために、成績が良くなくても海外の大学に進学できる「2つの方法」をご紹介します! コミュニティカレッジからの編入 アメリカ、カナダの場合、2年制大学「コミュニティカレッジ」の大学編入コースから4年制大学に入学することができます。 出願に必要なのは、次の書類です。 高校の卒業証明書(高等学校卒業程度認定試験合格証) 銀行の残高証明書 英語能力試験のスコア(IELTS5.5以上が多い) なそ、出願書類を提出すれば、ほとんどの人が入学できます。 基本的にコミュニティカレッジの成績結果のみで、4年制大学の3年目に編入できます。 そのため、日本での偏差値や出身校のレベルも問われずに、自分の努力次第で世界トップクラスの大学に入学できる大きなチャンスになるのです。 https://bokuryuu.com/community-college/ マレーシアの大学からの編入 高校卒業者の場合、1年間のファウンデーションコースを受けなければいけませんが、一般的な出願書類は次の通りです。 英語能力試験のスコア(IELTSスコア4.5以上) 高校の成績証明書・卒業証明書 英作文 ファウンデーションコースも必要書類を提出すれば、ほとんどの人が入学できます。 卒業後は3年制の大学に入学し、次の方法で世界トップクラスの大学の学位が取得できます。 デュアルディグリープログラム:マレーシアの大学+海外提携大学のバチェラーディグリーが、同時に取得できるプログラム ツイニングプログラム:卒業時にマレーシアの大学ではなく、海外提携大学のバチェラーディグリーが取得できるプログラム アメリカンディグリートランスファープログラム:アメリカの大学への編入を目指したプログラム https://bokuryuu.com/malaysian-education-system/#Bachelors_Degree まとめ ここでは、海外大学の偏差値や受験システムを理解するために、 そもそも海外大学に偏差値はあるか 海外大学の受験システムを理解しよう 合否審査の基準は成績だけではない 成績が良くなくても海外の大学に行ける方法 をご紹介しました。 大切なのは最終学歴! 偏差値に関係なく、書類審査で入学できる海外大学には、多くの人にチャンスをもたらします。 入学した後の勉強は大変ですが、数年間頑張ることで、人生を大きく変えることができるのも、海外の大学へ進学する醍醐味と言えるでしょう。 留学先選びの材料として、ぜひこの記事を参考になさってください! その他、留学ついて詳しく知りたい方は、ぜひ一度留学エージェント「ぼくらの留学」にご相談ください! 初めての留学を考えている 英語があまり得意ではない 時間があまりない 書類提出などで失敗したくない 留学費の節約方法のことが知りたい など、どのような方にも合わせたサポートを行なっています! ぼくらの留学をご利用いだたくメリットは次の3つです。 オンラインカウンセリング:日本全国、どこに住んでいてもお気軽にご連絡ください 留学代行手数料無料:留学費用が気になる方にも安心してご利用いただけます 留学準備から帰国後までアドバイス:「意味のある留学」を一緒に作っていきましょう! まずは、無料カウンセリングからどうぞ! https://bokuryuu.com/about-agent-of-studying-abroad/ 参考サイト 大学を選ぶコツ:www.princetonreview.com 大学偏差値マップ:hensachimap.net 大学入試偏差値ランキング:www.toshin-hensachi.com…
2022/01/03